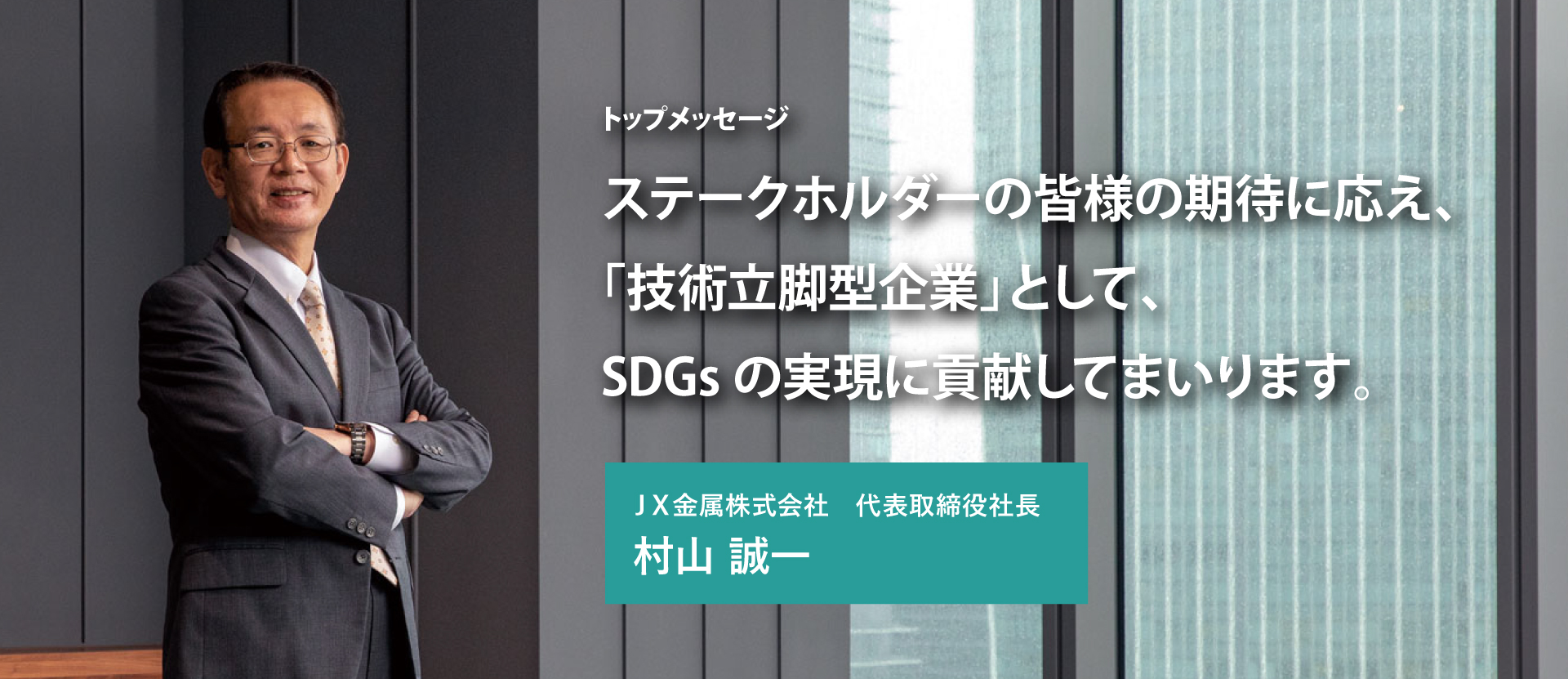
2020年度は、新型コロナウイルス感染症の猛威に始まり、世界の経済・社会に及んだ甚大な影響が期末まで継続した1年でありました。ご自身やご家族が罹患された方、事業の中断や停止を余儀なくされた方々には心よりお見舞いを申し上げます。
JX金属グループの事業活動においても予想以上に大きな影響があり、人の出入りの抑制など厳格な感染対策をとりながら事業を継続してきました。従業員は日頃の安全対策や健康管理に加えて、感染対策という大きな負担や制限を負いながら、生産・改善・省エネ活動等を維持してきました。現在もその努力は続いていますが、国内の各事業所においては幸いにも生産障害や生産制限に至らなかったことは、大変ありがたく思っています。
また、2020年度は私たちにとって非常に思い入れの強い中期経営計画の初年度でもありました。それは、当社グループが描いた2040年長期ビジョンへの導入であり、その種まきを行う上で重要な1年であったからです。振り返ってみると、グループ全社の尽力により、概ね着実な成果が残せたと評価しています。特に、成長戦略の要であるフォーカス事業の拡充については、スピード感をもって能力増強を進めることができました。背景には、コロナ禍によるテレワーク等の通信需要が急速に増大し、当社グループの機能材料、薄膜材料等に対する需要が格段に増え、非常に旺盛な受注状況が続いたことが挙げられます。それに対して現場が早期に呼応して増産を行い、お客様や社会のニーズに応じた供給責任を果たすことができたと思っています。
一方、ベース事業については、競争力の強化を行い、将来に向けた体制づくりを講じてきました。その要となる資源事業のカセロネス銅鉱山についてはクリーン鉱の増量による事業の強靭化を図るため、2021年2月に全権益の取得を完了しました。さらに、ベース事業のもう一つの柱である金属・リサイクル事業についても、リサイクル事業の強化のため、台湾の集荷拠点拡充および佐賀関近傍の物流拠点新設に取り組み、計画通りに進捗しました。残念ながら、カセロネス銅鉱山の操業については、感染対策のために操業人員が制限されたことにより減産となり、金属事業についても一部、鉱山側の供給障害による買鉱条件の悪化等がありましたが、銅価格・貴金属価格の上昇が収益を支えたこともあり、2020年度は最終的に増益を達成することができました。
これらの業績の原動力には、世の中が求めるデジタル社会の実現に欠かせない素材を供給しているという従業員の自覚と自負があったと捉えています。フォーカス事業、ベース事業ともに社会が必要とする素材を供給するサプライチェーンにおける当社グループの役割を強く認識しており、グループ全社が高いモチベーションで取り組んだ結果であると思っています。
2020年6月に行った本社移転も長期ビジョンへの施策の一環です。中計の戦略実行に伴う増員計画に基づいてキャパシティを確保したものですが、それ以上に大きな狙いは、私たちが目指す姿と掲げた目標を達成していく上で欠かせない、機動的な事業運営と付加価値創出型人材の育成を新しい職場環境で実現していくことにあります。新たな行動様式としてこれからの人材に求められていることは、イノベーションに向けた創造力です。新本社には、「技術に触れる」「高効率な働き方」「人と人をつなぐ」をテーマとしたさまざまな仕掛けが施してあり、本社をモデルとしてグループ全体の意識改革を進めていきたいと考えています。新本社では、ABW(Activity Based Working)を新たに導入し、働く場所・時間・方法を一人ひとりが自律的に選び、動き、何かを創造するという姿勢や企業風土を醸成していくことを狙いとしています。
2040年長期ビジョンとして、当社グループは事業の再定義を行うとともに、新たに「技術立脚型企業」への転身を宣言しました。これは、現在・未来の社会において、ベース事業を強靭な基盤としつつ、付加価値の高い差別化を図った先端素材で世の中に貢献していく意志を示しています。そのために必要な組織の体制、企業文化や風土とはどのようなものか、本中計ではそれを念頭に置いてさまざまな施策を打っています。さらに、ESG に対する取り組みが社会から企業価値を認めていただく一つの重要な物差しであると捉え、ESGへの対応を経営上の重要課題としました。
ESG経営の推進に当たり、2020年度は二つのことを実行しました。まず、当社グループの事業における重要課題(マテリアリティ)の見直しです。非鉄金属事業という特性を活かして持続可能な社会の実現に貢献していくために、どのような優先順位を付けるべきかという観点から取り組み、課題を改めて整理し直しました。さらに、グループ成長の中核となるフォーカス事業の使命である「くらしを支える先端素材の提供」を新たな項目として加え、目指す姿をより鮮明化しました。
そして、ESGを経営の重要課題としてしっかり取り組んでいく考えを形にするため、2020年10月にESG推進部を発足しました。これは全社目線でESG戦略を策定し、経営に反映させていくための組織であり、ESG推進部が中心となって課題に取り組むことを通じて、ESGへの取り組みに対する重要性・本気度を社内外に示すという役割も担っています。同部を中心に、まずは国際潮流とステークホルダーの要請を踏まえて、「気候変動への対応」「循環型社会への貢献」「国際規範・イニシアティブへの対応」の3点を重点項目に設定し、優先して対応を行っていくこととしました。また、本中計では、3ヵ年で3,000億円の設備投資を計画していますが、そのうちの200億円をESG 投資枠と定め、脱炭素をはじめとする諸活動の活性化を図ることとしています。

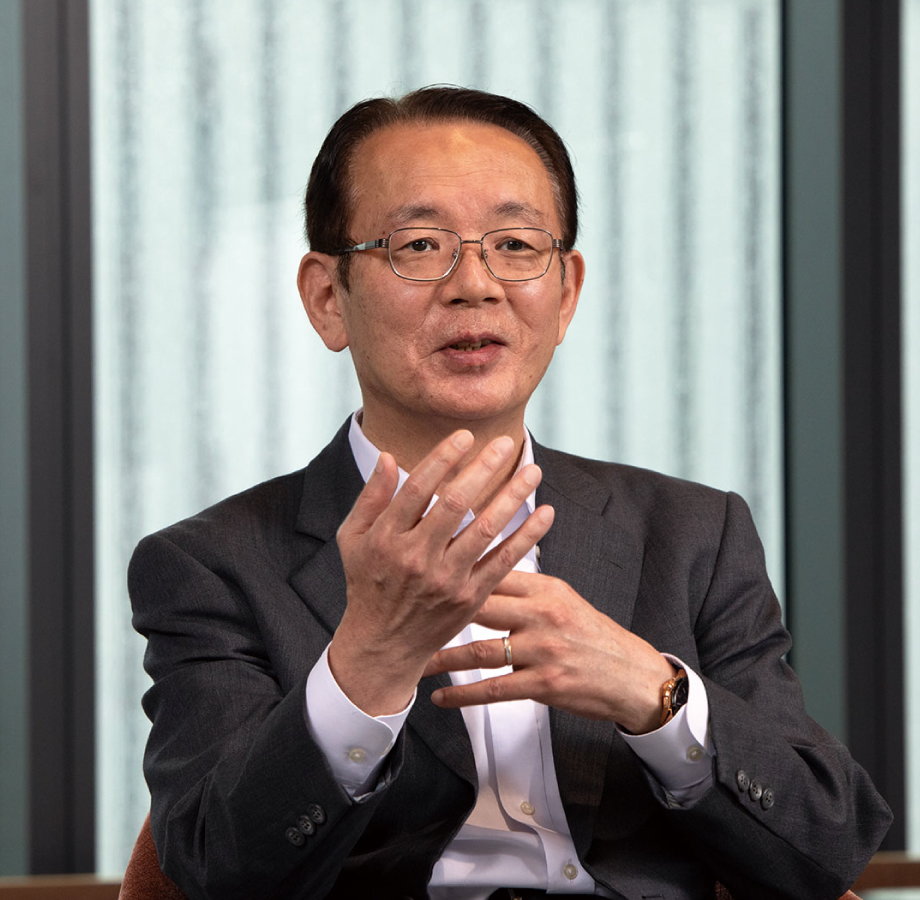
今後の企業価値向上を目指していくには、ESG経営の視点が欠かせないものであり、特に気候変動対策と循環型社会の構築に対する意識は、国際社会でもこれまでにない高まりを見せています。当社グループは当初、2040年度をターゲットに自社のCO2総排出量50%削減(2018年度比)、2050年度にCO2ネットゼロという目標を掲げていましたが、社会の趨勢を受けて私たちの動きを加速する必要があると認識し、中間目標のCO2総排出量50%削減達成時期を10年前倒しし、2030年度に改定しました。これを経営における重要な目標に据えて、しっかりと取り組んでいく考えです。
既に、この大きな目標に向けては、全社的活動がスタートしています。その皮切りが2021年1月に行ったカセロネス銅鉱山のCO2フリー電力への切り替えです。これは当社グループCO2総排出量の約60%を占める調達電力起源CO2の排出ゼロ化に向けた取り組みであり、4月から磯原工場および倉見工場、6月から佐賀関製錬所においても切り替えを実行しました。今後も全事業所の切り替えに向けて順次対応を進めていく考えです。また、調達電力をCO2フリーにするだけでなく、各事業所で再生可能エネルギーの創出も行っていきます。まずは中間目標の達成に向けた活動を着実に進めていますが、その先の最終目標までの道筋については、新たな発想を取り入れた技術開発が不可欠になると見込んでいます。
非鉄金属資源を扱う当社グループが真正面から取り組み、脱炭素および循環型社会の構築に貢献していく施策として、銅製錬におけるリサイクル原料比率を格段に高めるという目標にも挑戦していきます。リサイクル原料を使うことで、サプライチェーン全体でエネルギー消費を抑えるとともに、資源の有効利用を促進することができます。加えて、当社のリサイクル事業で長年手掛けてきたリチウムイオン電池(LiB)リサイクルの技術を活かし、EV普及を支える車載LiBの「クローズドループ・リサイクル」の確立にも挑んでいきます。
当社グループの非鉄金属素材はそもそもが再生可能エネルギーの普及やエネルギー効率向上に欠かせないものであり、付加価値の高い素材を安定供給していくことや先端素材により技術革新を促進していくことで、社会の脱炭素化および循環型社会構築の加速に寄与できると考えています。2050年度CO2ネットゼロの達成とともに、自らの技術によって持続可能な社会を現実のものとしていく、その意志をグループ全従業員と共有し、社内外に発信し続けていきます。
非鉄金属素材を扱っていると、世の中の変化が非常によく分かります。当社グループはその変化に対応し、絶え間ない創造と革新によって、社会に必要とされる非鉄金属素材を提供してきましたが、このサイクルはこれからさらに加速していくと見ています。変化のスピードに対応していくには、自らの立ち位置と変化する世の中が向かう方向にどんなギャップがあるのかを素早く察知できる能力が必要です。そのギャップは言い換えるとリスクであり、解消していくためには世の中を見渡して進む方向を見定め、走り出さなければなりません。これには、創造力と論理的思考、そして何より挑戦する姿勢が必要です。チャレンジを恐れていては、世の中の変化によって生じるリスクを解消することはできないでしょう。
当社グループの描いているありたい姿は、世の中が求めている社会の姿を現実のものとする高度な素材を自らの技術力で創出し、新たな時代の到来を導くということです。これは非常に大きなチャレンジですが、この姿勢がなければ企業として成長し続けていくことはできません。社会課題を解決に導く「最先端」を当社グループが支え続けていく、この構造とサイクルは創業から堅持してきたものであり、これからも決して崩したくないものです。
私たちはこれからもステークホルダーの皆様の期待に応え、皆様とともに新しい社会へ進んでまいります。