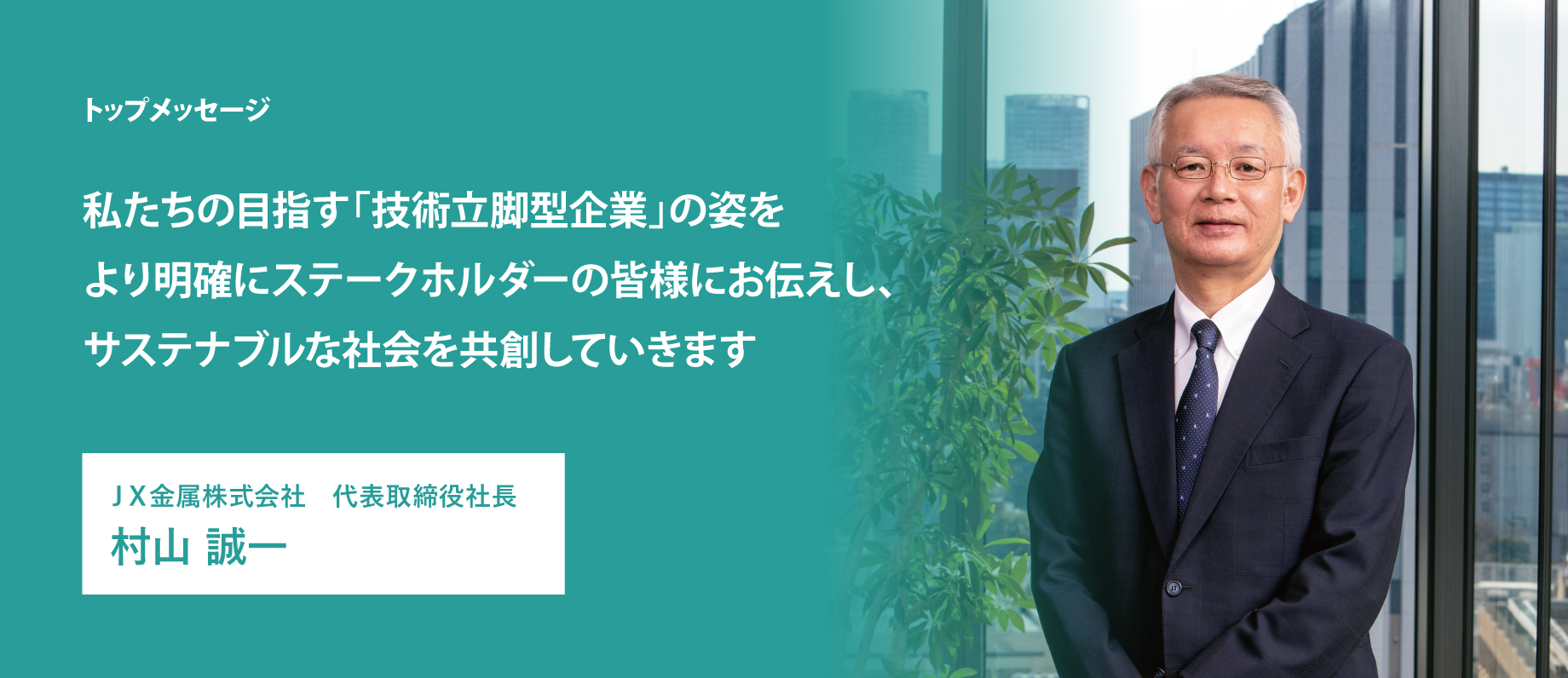
JX金属グループの2021 年度の連結営業利益は1,582億円と大幅な増益となりました。前年度は781億円でしたのでほぼ倍増となりますが、内訳をみると非鉄金属価格の高止まりと為替の円安影響が大きいのも事実です。ただ、そうした外部環境の追い風を除くと前年並みに留まったというわけではありません。特にフォーカス事業の機能材料や薄膜材料、タンタル・ニオブ事業等は外部環境を除いても大幅な増益となりました。これはスマートフォンや通信インフラ等の高機能IT分野でのマーケット成長が継続する中で、グループ一丸となって強みを持つ製品の増産・増販に努めた結果と言えるでしょう。
一方、ベース事業は市況の上昇と円安を享受することでこちらも増益となりました。まず資源事業では、2021年2月に100%権益を取得したカセロネス銅鉱山、持ち分権益を保有するエスコンディーダ銅鉱山およびロス・ペランブレス銅鉱山(いずれもチリ共和国)において、コロナ禍での操業を余儀なくされ、十分な人員体制が組めなかったこと等により、年間を通じて万全な生産を行うことが困難でした。これらはやむを得ない理由ではあるものの、課題も残す結果となりました。また、金属・リサイクル事業では、製錬とリサイクルの一体運営体制のもと、リサイクル原料の増処理、原料構成の最適化および各製造拠点の操業効率化に取り組んできました。新型コロナウイルスの感染拡大影響や海外でのリサイクル原料獲得競争の激化等、悪条件がいくつか重なったものの、一連の取り組み成果も実感しています。
2021年度から2022年度初めにかけて複数の大規模な設備投資計画を発表しました。当社グループは、2040年長期ビジョンのあるべき姿に基づく事業の再定義を行い、「技術立脚型企業」への転身を宣言しています。「技術立脚型」とは現在・未来の社会においてベース事業を強靭な基盤としつつ、付加価値の高い差別化を図った先端素材で、SDGsや持続可能な社会の実現に貢献することです。既に2021年度においてもこうした分野の市場成長は明確で、この機会をしっかりと捉えるための設備増強計画は、本中計でも主要なテーマとして取り組んできました。
2021年12月に発表したのが、半導体用スパッタリングターゲットおよび圧延銅箔の生産能力増強です。前者は日立市内の北部に、後者は日立事業所内にそれぞれ新工場を建設するものです。これまでも両製品の生産能力増強を進めてきましたが、足元で急拡大する需要に機動的に対応するため、さらなる投資の実行を決定しました。2023年度からの次期中計期間中の市場の伸びに対応する設備投資と位置付け、300億円規模を予定しています。次期中計を見据えるという点で、タンタル・ニオブ事業では、タニオビス・タイ工場への投資を決定し、機能性タンタル粉末を現状の3割程度、生産能力増強を図る計画です。また、タンタル・ニオブ事業から薄膜材料事業へのサプライチェーン強化のため、タンタルインゴット製造を担う東京電解(株)の完全子会社化を実施しました。
2022年3月には 茨城県ひたちなか市に新工場建設 のための大規模な用地取得を公表しました。新工場は次期中計のその先を視野に入れ、先端素材分野を中心とした新たな主要拠点としていく予定です。半導体、電子デバイス分野の需要の伸びは今後も長期的に継続すると見込まれ、複合工場を建設するとともに、茨城県内に本社機能の一部を移転することを含めて検討しています。新工場への投資総額は詳細を精査中ですが、工場投資としては過去最大の規模になる見込みです。
さらに米国のアリゾナ州に大規模な用地取得を行いました。アリゾナ州は半導体産業の集積地であり、今後さらに半導体用スパッタリングターゲットの生産能力を顧客ニーズに応じて機動的に拡大していきます。それだけではなく、約26万平方メートルの広い用地を活用し、北米における先端素材分野の中心地としていく考えです。
ベース事業についても、当社グループの成長を支える基盤となる事業として、グループの土台を強靱化すべく、一層の競争力強化を図っていく必要があります。「グリーンハイブリッド製錬」進化のため、直近ではJX金属製錬(株)佐賀関製錬所を中心に金属・リサイクル事業の強化に資する投資を複数行いました。一例として、大分市内に物流センターを新設し、同製錬所内のリサイクル原料の処理設備を増強しましたし、リサイクル原料の集荷を強化するため、2022年8月にはeCycle Solutions Inc.の買収を発表しました。同社は、カナダ・オンタリオ州の主要拠点をはじめ、同国内8ヵ所に拠点を持ち、強固な集荷ネットワークを有すE-waste(廃家電・廃電子機器)回収・処理事業者であり、同国において最大のシェアを有しています。また、事業強化のための選択と集中も進め、インドネシアのP.T. Smelting、韓国の製錬会社LS-Nikko Copperの株式売却を決定しました。一方で、サプライチェーンの強化策として、硫酸輸送基盤の強靭化を目的に北豊運輸の株式取得も実施しました。
当社グループは、ESG を経営上の重要課題に定め、持続可能な社会の実現に貢献していくことを宣言しています。この1年を振り返っても、脱炭素をはじめとするSDGs・ESGの世界の潮流はより顕著になり、加速していると言えるでしょう。2021年度に取り組んできた戦略的な投資や施策のほとんどが、ESGの観点からも重要なものとなります。
銅を中心とした非鉄金属は今後も需要が増大していくだけでなく、当社は独自技術に立脚し、より付加価値の高い先端素材に姿を変えることを通じて、社会に貢献することが求められます。脱炭素を巡っては、既に電気自動車(EV)の普及をはじめとするあらゆる分野での電動化や再生可能エネルギーの導入の動きが拡大しています。これらを可能にする技術革新に欠かせない非鉄金属やその先端素材を供給する当社の事業そのものがSDGs・ESGに貢献し、成長を続けるという確信を持っています。また、こうした非鉄金属や先端素材は原料調達や生産過程においてもSDGs・ESGの観点が求められます。
当社グループのそのような考えを表したのが、2022年8月に発表した 「サステナブルカッパー・ビジョン」 です。銅は持続可能な社会に貢献する非鉄金属であり、その需要は今後も伸びていきます。将来にわたって銅を安定供給していくこと、脱炭素や資源循環等のESGに配慮した形で生産することを当社グループの使命と位置付けました。具体的には、銅の製錬において、従来以上にリサイクル原料を多く使用するグリーンハイブリッド製錬を通じてサステナブルな生産・供給を進化させ、このような形で生産された銅が省資源、省エネ、省カーボンすべてにおいての最適解であることを世の中に訴求してまいります。そして、この私たちの考えに賛同していただける企業や団体の皆様を募って、Green Enabling Partnership を形成し、この輪を広げていきたいと思っています。
資源循環やサーキュラーエコノミーの観点ではリチウムイオン電池(LiB)のクローズドループ技術の開発に取り組んできました。日立事業所の技術開発センターへの実証設備の設置を経て、量産技術を確立するためにJX金属サーキュラーソリューションズ(株)を2021年春に設立しました。海外、特に欧州は日本以上に資源循環を求める動きが強く、2020年末にLiBを含めた電池一般に対するリサイクルが義務化されました。この分野で先行する欧州の規制に準拠した競争力のあるビジネスモデルを構築すべく、JX Metals Circular Solutions Europe GmbHやTANIOBIS GmbH(いずれもドイツ連邦共和国)を含むグループ一丸となって取り組みを進めています。その一環として、2022年6月にフォルクスワーゲングループを核とする産官学の新しいコンソーシアムHVBatCycleへの参画を決定しました。これは車載用LiB材料の回収および再利用に関する共同研究開発を目的としたものです。世界的なEVの急速な普及を踏まえると、2030年前後には実際に車載用LiBが大量廃棄される見込みです。またEVの普及に伴い、車載用電池に必要なニッケル、コバルトやリチウムの需要も大幅に増加し、それらを鉱山などの天然資源にのみ求めることは不可能でしょう。電池材料のEVからEVへのリサイクルを可能とするクローズドループによるリサイクルが社会的にも経済的にも最適解の一つであることはパートナーの間でも共通の理解になりつつあります。これらの希少資源をサステナブルに供給していくことに貢献する仕組みの一部として当社グループの技術が役立てると考えています。
2020年度に社会の要請や変化を踏まえて、当社グループが優先的に取り組む 重要課題(マテリアリティ) を改めて抽出しました。このうち、「くらしを支える先端素材の提供」についてはこれまで説明した通りです。「地球環境保全への貢献」については、前述のサステナブルカッパー・ビジョンやLiBクローズドループへの取り組みだけでなく、気候変動戦略 として当社自身のCO2排出についても、より積極的に削減すべきとの考えのもと、CO2排出量削減の中間目標を10年前倒しすることを宣言しました。現在、「2030年度までにCO2自社総排出量2018年度比50%削減、2050年度ネットゼロ」という大きな目標を掲げて全社横断で活動を進めています。今中計においてESG投資枠を設定して設備投資や技術開発を促すとともに、国内外の事業所におけるCO2フリー電力への切り替えを推進してきました。2022年7月には、非鉄金属業界として初の「トランジション・リンク・ローン・フレームワーク(TLLF)」を策定し、日立北新工場(仮称)の半導体用スパッタリングターゲット生産拠点における環境対応費用としてTLLFの活用に基づくトランジション・ファイナンスを組成しました。また、CO2排出量のScope3相当分の定量化も進め、これらを総合したTCFDに基づく情報開示もより充実させるべく取り組んでいます。
当社の目指す長期ビジョン達成のためには、新しいビジネスを連続的に生み出す企業体へと変化していかなければなりません。それには創造力ある付加価値創造型の人材が不可欠であるとの認識のもと、「魅力ある職場の実現」にも取り組んでいます。2020年6月に本社移転とABW(Activity Based Working)の導入を行い、新しい働き方として定着していますが、個々人の多様な働き方や価値観を尊重しながら付加価値創出に資するコミュニケーション環境をつくることを主たる目的としています。また、新型コロナウイルスの感染拡大もあり、テレワークも急速に定着しましたが、一方で対面でのコミュニケーションを重視していくことも組織の活性化やイノベーションの創出には不可欠だと感じています。

私自身、社員と接する機会に必ず話しているのは、当社のDNAである仕事本位のコミュニケーションを大切にし、さまざまな人と議論しながら業務や課題に取り組むことの意義です。そもそも技術立脚型企業には社会の変化を鋭く捉え、創造力を発揮することが求められ、それらを伴わない企業はいずれ淘汰されていくと考えています。そして創造力は、現状に甘んじる考えを持っていては生まれません。オープンイノベーションを積極的に行い、多種多様な知見に接し刺激を受け、吸収することを通じて、組織内部を活性化させるべく闊達な議論を行うことが、当社らしいやり方なのではないかと考えています。
当社グループは幸いにして、今後も社会のニーズがより高まっていく素材を扱っています。しかし、マーケットの変化はますます早まり、要求も高度化することから、10年、20年、30年後も今と同じように当社が成長を続ける保証はありません。次の瞬間にもこれまでとは異なる特性や、より高度な性能や品質が求められることもあり、これに技術で応えることができなければ、当社のビジネスは大きな苦境に立たされることでしょう。世界の非鉄金属企業に対し、当社が確固たる優位性を持っていること、こうした技術立脚型企業の実現に向けた事業基盤の確立を目指して デジタルトランスフォーメーション(DX)戦略 も加速させています。
これからは従業員のみならず、当社の事業や取り組みをもっと社会に認知していただき、「地域コミュニティとの共存共栄」を高めていくことはマテリアリティの一つであり重要な経営課題です。そして、当社と同じベクトルを持ち、同じコンセプトで取り組んでいける地域、大学・学校や団体と、企業においてはスタートアップから大企業まで、いつでも共創に取り組む用意が当社にはあります。2040年の長期ビジョンの実現に向けて自前主義にこだわる必要はないと認識しています。あらゆる分野の方々とともに目指す社会を実現していく、そのために私たち「JX金属グループの姿」をよく見ていただけるよう、積極的な情報発信を行っていきます。今回のサステナブルカッパー・ビジョンの発信はその象徴とも言え、当社として取り組みを加速させる意思表示でもあります。今後、業種を超えたさまざまなパートナーとの連携・協業(Green Enabling Partnership)を通じ、サーキュラ―エコノミーを実現していきたいと思います。